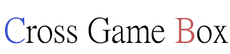それは優雅な昼の一時となるはずであった。太陽の光が窓から射し込み絨毯に四角い模様を彩る休日の昼に、前日に買っておいた赤福を日本茶をすすりながら食べる。紗彩にとって武道に打ち込む緊張感に満ちた日々から解放される数少ない時間であった。
しかし、楊枝で折箱に並んでいる赤福を刺して口に含もうとしたその時、紗彩の頭の右上にもやがかかったようなうっとおしい感覚が生じて次に背中の肩甲骨周りの筋肉が硬直した。まるでリングの上で強者を前にした時のような身体の反応であった。
虫の知らせというやつなんやろか……。赤福が刺さった楊枝を手にしながら紗彩はふとそう思った。日本で昔から使われている言葉であるが、紗彩自身これまでに体験したことは一度もない。だが、なんとなくこれはそうなのではないかという強い思いに駆られた。
思い当たる節は一つだけであった。執行機関の一員である天王寺咲が対外試合に出ているのである。執行機関とは女子ボクサーに限定した対外試合、いわば道場破りを専門に担う武闘派ボクサーの集まりである。紗彩はその機関の長を務めている。
しかし、対外試合といっても対戦を申し込む予定である村上ユキナは弱くはないが目を見張るほどの何かがあるボクサーでもない。咲が負けることなどまずない。しかし、何が起きるかが分からないのがボクシングでもある。
紗彩は楊枝を折箱に置くと椅子に座ったままでいた。何もせずに前を見据えただ時間だけが過ぎていく。窓から差し込む太陽の光で暖かった部屋は西日と共に寒気が流れ始め、窓の外が暗くなり冷え切った頃、紗彩の携帯電話が鳴り始めた。紗彩は手に取って電話に出る。
電話は愛染奏からだった。ただならない様子であることは奏の重い口調からすぐに分かった。それでも、紗彩は「どうしたんや?」と柔らかく応答をした。
そして、咲の敗北を奏から知らされた。
悪い予感が的中した。咲が負けるはずがない。なぜこんなことが起きたんやろ……。動揺し自身に問いかけながらも紗彩は機関のボスとして冷静に奏からの言葉を聞き続けた。そして、思いもしない展開が起きたことが分かった。
咲が負けたのは村上ユキナではなかった。村上ユキナが所属するジムに咲が行き、対外試合を申し込むと、その場が荒れた。対外試合など認められないという反応をジムの者たちが示す。それは周りで練習する門下生だけでなく、ユキナまでもが同じ反応をみせていた。対外試合の申し込みをしに行き何度となく目にしてきた光景だというのに、咲ははぁっとため息を出した。これほど萎える時もない。当の本人が闘う気がないのだから試合をする意味はない。咲が帰ろうかしらとしたその時、ジムの奥から咲に向かって声が送られた。
「勝つと分かっている相手と試合をして何が面白いというの?」
予想だにしていなかった言葉、そして自身が今まさに胸に抱いていた思いを代弁するかのような言葉。心がわくわくと震え始めた咲は、その言葉を発した当人の方に顔を向ける。
言葉の主は金色の髪をして碧い瞳の若い女性であった。欧米の人間にちがいなかった。ロンドンで生まれ育ち幼い頃から見慣れていたとはいえ、欧米の女性を日本のジムで見るのは咲にとって初めてであり、面を食らっていると、金色の髪をした彼女は続けた。
「あなたが勝つことは目に見えているわ。あなたもそう思っているのではなくて?」
確かな眼力を持ち強者の風格を漂わせるように彼女は言う。それは咲にとってたまらない言葉であった。咲の口元がにんまりと緩む。
「試合をしたいのならわたしと試合をなさい」
当初の予定と変わることになるが、悩むまでもない。咲は金髪の女性からの申し出に応じ、二人はともにリングに上がった。
試合は5ラウンドに咲がKO負けをした。負けたといっても完全な力負けではなかった。ダウンも一度奪っている。5ラウンドにダウンを奪い返され、立ち上がり再会したところにとどめのパンチをもらい試合を決められた。詰めを間違えなければ勝てたかもしれない試合。それでも負けは負けである。
咲の敗北を知った紗彩は電話を切ると、ふぅっと息を吐きながら天井を見上げた。手から携帯電話が落ちても気にも留めずに天井を見続けるのだった。
翌日、執行機関のメンバーたちはいつも使用している雑居ビルの一室に集まった。緊急の会議を開き、咲の敗北を受けてこの先どうするかを話し合った。どうするといっても今後の活動は話し合うまでもなくほぼ決まったも同然である。誰と試合をするかではなく、誰が試合をするかである。咲を倒したセシリア・レイフィールドと名乗る欧米人を相手に誰が咲の仇を討ちに出るかである。
紗彩が希望する者を聞くまでもなく、ボスの懐刀である奏が真っ先に名乗り出た。それを合図に少女たちは競うように自分がその役目を果たすと言い合った。紗彩と咲を除く三人が引かずに自分こそが相応しいと言い合う。それはやがて自分の強さを主張したり立候補する者の弱点を指摘したりと口喧嘩の様相を呈していく。そんな面々の言い合う姿を目にし、紗彩は緊張するこの場において口元が緩んでいく。
強い相手と試合をしたいと日頃言葉にする機関の面々であるが、そうではない。みんな執行機関で共に闘う仲間たちのことが大好きなのである。大切な仲間が敗れたから自分がかたき討ちをしたいと一歩も退かない。そんな執行機関の面々を紗彩も大好きなのだ。だから、紗彩は躊躇していた決断をくだすことが出来た。
「今回はうちがやらしてもらう」
メンバーたちが立候補し言い合っている間、沈黙していた紗彩がそう言うと、他の少女たちが紗彩の方を一斉に向いた。
「ボス、どうかお考え直しを。リーダーであるあなたまでが負けたら執行機関は壊滅に繋がります」
懐刀である奏が真っ先にと紗彩を止める。しかし、紗彩は考えを曲げない。
「執行機関が同じ相手に二連敗しても機関の威信は地に落ちるやろ。誰が負けても結末は同じ道を辿る。そやから今回はうちがやらしてもらう」
温厚な彼女だが一度決めた決断を覆さない頑固な性格でもある。それでも奏も引き下がるわけにはいかない。紗彩が間違った判断をした時には自分が止めなければならない。機関のナンバー2の座にいる彼女はその責務を負わなければならないと自身に課していた。
「だからといってボスが出ることはないでしょう。いつものように重要な案件は私が行うよう命令してください」
一歩も退かない主張の言い合いは紗彩と奏の間に変わっていた。だが自身の、いやボスとしての命令に従わない奏を前に紗彩は苛立つどころか彼女は普段の温和な表情をさらに柔らかくする。
「ほんまに…ありがたい言葉やな、奏。でもな……」
紗彩の目が瞑るくらいに細まる。
「もう機関のメンバーが負けるのを見たくないんよ」
何もかもを包み込むようなその柔らかな笑みは菩薩のようであった。
「でも……」
それでも食い下がれない奏に、
「分かってあげなよ奏」
咲が言った。
「ボス以外の者ではまた負けるかもしれない。それだけの相手だと判断したのよボスは」
自身を倒した者を賞賛する。人前で言葉にする悔しさを吞みながらも咲は両腕を左右の手で抑えながら冷静に言った。
試合に負けた咲の一言の重みの前にもう異論を唱える者はいなかった。
一週間後、紗彩は咲が対外試合に出て敗れた井崎ジムへ行った。一週間と時間を空けたのはセシリアが試合で負ったダメージを抜かせるためである。本来ボクサーはもっと期間を空けて試合をする者だがそれはプロに限られた習慣であり、地下ボクサーにとって一週間という期間は静養に十分な時間である。もっともセシリアが地下の者であるのかは分からないが。
しかし、ジムに着くとまたも予想していない事態に紗彩は直面した。井崎ジムにセシリアは所属していなかったのである。二週間前から体験入門でジムで練習するようになり咲と試合をした翌日に入会は見合わせる旨の連絡の電話がセシリアからきて、それ以降彼女は一度もジムに来ていないのである。
紗彩はセシリアの情報を聞こうとジムの者に聞いたが誰も彼女のことを名前とイギリス人であること以外知らなかった。住まいの住所も分からないのだから彼女の行方を探す一番の手掛かりはボクシングジムに他ならない。紗彩は都内のボクシングジムをしらみつぶしに足を運んだ。だが、全てのボクシングジムを訪れてもセシリアは所属してるどころか彼女の名前すら知る者はいなかった。
あれほどの実力の持ち主でありイギリスの女性であるのなら一目見たら印象にくらい残ってもいいものだが、彼女のことを知る者は誰もいない。彼女は一体何者なのだろう……。無論、インターネットで彼女の名前で検索することは真っ先に行ったが検索には一件も引っかからなかったし、機関専属の情報屋である文菜にこの件を依頼しても手掛かりとなる情報さえ一つも出てこなかった。
セシリア・レイフィールドの行方を探してから二ヶ月が経った頃には完全にお手上げな状態となっていた。
「イギリスに帰ったんじゃないですか」
喧騒する街並みを歩きながら、セシリアの行方が分からないとぼやく紗彩に対してそう言ったのは咲であった。機関において最もセシリアと試合をしたいであろう咲が淡々と言った。まったく推測でしかない意見だが最も可能性が高い考えであることは紗彩にも感じられた。しかし、その最もありうる事態だけは起きないでいて欲しかった。国内で探すのとイギリスで探すのでは手間と労力に天と地ほどの開きが出てしまう。
「そやったら毎日神社に行くしかなくなるわ」
「何ですかそれ」
咲が呆れた顔で紗彩を見る。
「セシリアが日本にいて近いうちに会えますようにって願うしかなくなるやない」
「そもそもセシリア・レイフィールドって名前が本名かも怪しくなってきましたよね。偽名の可能性だってあるじゃないですか」
咲は冷静にまたややこしい事態となる可能性を指摘する。
「それやったら咲を倒した相手とまた会えますようって願いを変えるわ」
「止めてよくださいそれだけは絶対に」
咲が足を止める。
「どうしたん」
と紗彩が咲の方を振り向くと、咲が呆然と口を開けながら右手で前を指していた。
「前?」
そう言いながら紗彩も釣られるように指先を追う。
そこには大きなセシリアの顔があった。ビルの外観に設置されている巨大なテレビのモニターにセシリアの映像が映されているのだった。
その映像はCross Game Boxという新しく発足した女子ボクシングイベントの宣伝番組だった。その女子ボクシングの大会にセシリアが参加選手の一人として紹介されたのだ。
「神様、粋な計らいするやない……」
紗彩は目をきらきらち輝かせながらそう呟くのだった。
翌日、紗彩はCross Game Boxを運営する機関の事務所へと足を運んだ。松原紗彩は地下の世界に生きる女子ボクサーだ。それでも彼女の名前は表の世界でも広まっており、Cross Game Boxを主催する機関も彼女の名前を出されて邪険に追い返すことはせずに中へと通された。
傘を持っていた紗彩が一階の通路を歩くと傘から垂れ落ちる雫が床にシミを作っていく。一番奥の部屋と通された紗彩はその部屋に一人でいた女性に対して用件を伝えた。長い黒髪をした年齢が30前後であろうその女性は一河しずると名乗り、紗彩のお願いを聞いたが、その反応はやはりつれないものであった。
「関係者ではないあなたにセシリアさんの所属するジムを教えるわけにはいかないでしょう」
紗彩は何度も頭を下げたが、しずるの応答が変わることはなかった。CGBの運営側が参加選手の個人情報を教えない対応をすることは紗彩も重々承知していた。それでも事務所まで訪れたのはセシリアの居場所を知る最速の手段であったからだ。最速であり最も可能性の低いであろう手段。それが駄目であったと分かり、紗彩は頭の中を切り替える。次なる方法はCGBの事務所の前で毎日張り込むことだ。時間はかかるし確実性もそれほど高くはない。しかし残る手段となるとこれくらいしかないだろう。
紗彩が「時間取らせてしまい申し訳ありませんでした」と詫び、しずるに背を向けて扉へ向かう。
「セシリアと接触する方法が一つだけありますよ」
紗彩の足が止まる。しずるへと再び振り向くと、彼女はそれまで事務的であった表情に口元に微笑ともいえる笑みが浮かばれていた。
「Cross Game Boxにあなたも出場すればいいじゃないですか」
「うちが……」
紗彩はぽつりと漏れるように呟いた。執行機関を立ち上げ地下ボクサーとして生きる道を選んでから表のリングに上がることは諦めていた。華やかなプロのリングに上がる資格を喪失したと。
「うちは執行機関の長としてこれまで数々の対外試合をしてきたんよ。いわば道場破りのようなものや。道場破りはボクシングの世界では御法度。それを知っていて言っているん?」
紗彩が確かめる。
「一ヶ月前の私でしたらあなたを誘うようなことはしていなかったでしょうね」
しずるはそう言い右手を口元に付け軽く笑う。
「地下ボクサーであるとか道場破りであるとか、セシリアの過去を知った今ではそのようなものを気にしていることが馬鹿馬鹿しくなってきたんですよ」
しずるの口元がさらに緩んだ。異様な笑みに紗彩には映る。
「セシリアに何があるって言うん?」
あの女には何かがある。紗彩も薄々感じていたことを目の前の女性は知っている。そう思うと遠回しに言わずに早く教えて欲しい衝動に紗彩は駆られる。
「私の口からは何も申し上げられません。セシリア本人に聞いてください」
肝心な話なるとしずるはまた事務的な対応に戻ってしまう。振り回れているようで紗彩は苛々する。
「まぁええわ。そっちが受け入れてくれるんやったら、あんたの主催するリングに上がったる」
しずるの笑みが正常なものへと変わり、ぱんと両手で柏手を打った。
「決まりですね」
紗彩のCross Game Boxへの参加が決まり、しずるから渡された契約書にサインをすると、事務所を出た。
雨はもう上がっていた。隣の建物の一階を覆う屋根からはまだ雫がポタポタと垂れ落ちているが、道路のアスファルトの地面に立つと、雲と雲の間から射す陽の光に紗彩はしばし目を向けた。
「まさかうちが表の世界のリングに上がることになるとはなぁ……」
お天道様に報告するかのように紗彩は陽の光を見てそう呟くのだった。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から